内容が最新ではない可能性がございますので予めご了承ください。
大量の顔汗にひそむ病気とは?
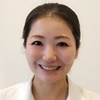
汗をかいて顔から汗が出るのは生理現象ですが、その量があまりにも多い場合や、何もしていないときに顔汗が大量に出る場合は病気の可能性があります。ここでは、ドクター監修のもと、顔汗の原因や病気との関連について解説します。

顔汗は特別なことではありません。汗は、暑いときや運動をしたとき、興奮をしたときや熱いもの・辛いものを食べたときなど、誰でも出るものです。しかし、何もしていないのに常に汗がにじんでいる、緊張したときにポタポタとしたたり落ちるほど汗が出るなど、その量が異常に多い場合は、なにかしらの病気がひそんでいる可能性があります。顔汗と関係する病気について、詳しく解説します。
顔だけに汗をかく病気とは
体のほかの部分はそうでもないのに、いつも顔だけに異常なほど汗をかくという場合は、「顔面多汗症」の可能性があります。
発汗には、上がりすぎた体温を下げるために起こる「温熱性発汗」、緊張・興奮したときに起こる「精神性発汗」、刺激の強いものを食べたときに起こる「味覚性発汗」があります。こういった生理現象の範囲を超えて大量に汗が出てしまう病気を「多汗症」といい、中でも顔だけに特に多く症状が現れるものを指して顔面多汗症といいます。
顔面多汗症の原因は未だはっきりとしたことがわかっていませんが、発汗を促す交感神経が過敏になっていることが関係していると考えられています。また、遺伝的な体質によって起こるケースもあるとされています。
顔汗と、異常な全身の汗かきから疑う病気
顔だけに限らず、全身に大量の汗をかいてしまう場合は次のような病気の可能性があります。
甲状腺機能亢進症
新陳代謝を活性化させる「甲状腺ホルモン」が過剰に分泌される病気で、代表的なものに「バセドウ病」があります。全身の代謝が高まるため汗をかきやすくなるだけでなく、動悸や息切れ、イライラ、食欲旺盛でよく食べるのに痩せるなど、さまざまな症状が現れます。
自律神経失調症
呼吸や体温、血液の流れ、内臓の働きなどを自動的に調節して体の恒常性を維持している「自律神経」のバランスが乱れることで、体にさまざまな不調が現れる病気です。発汗も自律神経がコントロールしているため、自律神経失調症になると汗が異常に出ることがあります。
更年期障害
加齢にともなう卵巣機能の低下によって女性ホルモンの分泌が低下すると、自律神経のバランスが乱れてしまいます。すると、血管の拡張や収縮をうまくコントロールできなくなり、汗が出たり、顔がほてったり、のぼせたりする「ホットフラッシュ」という症状が起こることがあります。
糖尿病(糖尿病神経障害)
糖尿病で血糖値が高い状態が続くと、末梢神経が障害される「糖尿病神経障害」になることがあります。自律神経も末梢神経の1つなので、その働きが低下すると発汗異常や立ちくらみ、便秘、下痢、尿意を感じないなど、体にさまざまな症状が現れます。
顔の片側だけに汗をかく病気
汗が出るのが顔の片側だけの場合は、「大動脈瘤」や「縦隔腫瘍(じゅうかくしゅよう)」の可能性があります。大動脈瘤とは、心臓から送り出された全ての血液を運ぶ「大動脈」にコブができることです。縦隔腫瘍は、「縦隔(左右の肺と胸椎、胸骨に囲まれた部分)」の中に発生した腫瘍のことで、どちらのケースも、その部分の交感神経が刺激されることで顔の発汗異常が起こることがあります。
多量の汗には、ただ単に汗っかきなだけの場合と、多汗症などの病気が潜んでいるケースがあります。リラックスしているときでも顔汗が気になるなど、なにかしらの異常を感じる場合は、その他の病気が潜んでいる可能性もあるので、専門医に相談してみましょう。
オススメ記事
- 関連するオススメ記事がありません。
スキンケア基礎講座
- スキンケア基礎講座
- アロマテラピー
- クレンジング
- サプリメントの基礎
- サプリメントを学ぶ
- スカルプケア
- スキンケアの基本
- ヘア・髪の知識
- ボディケア
- 妊娠・出産・産後の肌
- 心とスキンケア
- 更年期のスキンケア
- 産後の肌とスキンケア
- 美容・美肌
- 美容によいとされる植物
- 美容成分の基礎知識
- 美白・抗酸化
- 美肌をつくる化粧品の基本
- 美顔器を使ったスキンケア
- 肌と女性ホルモン
- 赤ちゃんのスキンケア
- 頭皮のケアについて
- メイク講座
- 悩み別講座
- アトピー性皮膚炎
- いぼ
- かゆみ・皮膚掻痒症
- シミ・そばかす
- シワ
- すそわきが
- その他の発疹・皮膚病
- たるみ・ほうれい線
- デリケートゾーン
- ニキビ・吹き出物
- ヘルペス
- ほくろ
- まつげのトラブル
- むくみ
- わきが
- 体臭
- 便秘・デトックス
- 傷・傷跡
- 冷え性
- 口内炎・口周辺のトラブル
- 多汗症
- 女性のお悩みボディケア
- 性病・性感染症
- 日焼け・紫外線対策
- 毛嚢炎
- 毛穴・角栓
- 水虫・皮膚真菌症(白癬)
- 汗・ニオイ
- 湿疹・皮膚炎
- 火傷(やけど)
- 生理痛・生理前の不調
- 白斑
- 目の周辺のトラブル
- 粉瘤(ふんりゅう)
- 糖質制限
- 美白・くすみ・目の下のくま
- 肉割れ
- 肌のハリ・ツヤ
- 脱毛・ムダ毛処理
- 花粉症
- 蕁麻疹(じんましん)
- 虫・害虫の皮膚トラブル
- 赤ら顔
- 靴擦れ
- 頭皮疾患・脱毛症
- 顔の傷
- 顔太り
- 用語集
- お肌&からだ・用語
- スキンケア・用語
- 化粧品・用語
- 美容成分・用語
- 男の美容講座
- お悩み&トラブル肌講座
- メンズスキンケア基礎講座
- 育毛
- 美容医療
- アンチエイジング
- くま・目の下のくま
- シミ(しみ)・肝斑
- しわ(注入治療)
- タトゥー(刺青)除去治療
- たるみ・ほうれい線治療
- ニキビ治療
- バスト・胸のお悩み
- ボトックスの治療
- わきが(ワキガ)のお悩み
- 二重手術
- 切らない脂肪吸引・部分痩せ治療
- 女性の増毛(植毛・ウィッグ)
- 脂肪吸引
- 赤ら顔・肌の赤み
- 鍼灸(しんきゅう)治療
- 肌タイプ別講座