内容が最新ではない可能性がございますので予めご了承ください。
とびひって何?どのような状態?
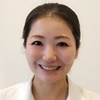
とびひは、皮膚症状をともなう病気です。掻くことで、またたく間に全身へと広がるため、正しい対処法を知っておくことが大切です。ここでは、とびひとはどのような状態なのか、原因や治療法などを含めてドクター監修の記事で解説します。

とびひが疑われた場合は、患部を触らずに医療機関を受診しましょう。受診の必要性を認識できるよう、症状について把握しておくことが大切です。とびひは、大きく2つのタイプに分類され、それぞれ症状が異なります。
とびひ(伝染性膿痂疹)とは
とびひとは、正式には伝染性膿痂疹(でんせんせいのうかしん)といい、主に乳幼児がかかることが多いとされています。細菌感染によって水泡や膿疱が現れ、掻くことで広がります。火の粉が飛ぶように症状が広がっていくため、「とびひ」と呼ばれています。とびひには、水疱が現れるタイプの水疱性膿痂疹と、かさぶたができるタイプの痂皮性膿痂疹(かひせいのうかしん)があります。それぞれ現れる症状が異なるので、確認しておきましょう。
とびひの症状
水疱性膿痂疹では、小さな水疱が現れ、次第に内部が膿で満たされるようになります。この水疱は破れやすく、破れると皮膚がただれた状態になり、患部の周りが赤くなります。掻くことによって、患部が拡大します。手に細菌が付着した状態で他の部位を掻くことで、最初に症状が現れた部位から遠い部位にも症状が現れます。
痂皮性膿痂疹の初期症状は赤い腫れです。次第に膿疱が多数現れるようになり、破れるとただれて厚いかさぶたを形成します。痛みをともなうことが多く、発熱する場合もあります。症状が悪化すると、原因菌が血液中に入り込み、敗血症という重篤な状態に陥るおそれがあります。また、腎臓に悪影響が及ぶこともあるため、早期の受診が大切です。
水疱性膿痂疹は子供に多く、痂皮性膿痂疹は大人に多いとされています。特に皮膚のバリア機能が低下しているアトピー性皮膚炎の患者はかかりやすいと言われています。
とびひを起こす原因
とびひの原因はどちらも細菌感染ですが、主な原因菌が異なります。水疱性膿痂疹の原因菌は黄色ブドウ球菌です。傷口などから皮膚の内部へと侵入した黄色ブドウ球菌が増殖すると、その際に表皮剥脱毒素(ひょうひはくだつどくそ)が生産され、これによって水疱が作られます。
痂皮性膿痂疹の原因菌は、A郡β溶血性連鎖球菌です。皮膚の内部に菌が侵入することで発症します。また、水疱性膿痂疹の原因である黄色ブドウ球菌との混合感染によって発症することもあります。
とびひはうつるのか
とびひは、掻くと周りに広がるという性質を持つため、他人にもうつると思われがちですが、厳密にはとびひはうつりません。黄色ブドウ球菌は皮膚の常在菌であるため、とびひの患者の黄色ブドウ球菌が人の皮膚に付着してもとびひを発症する心配はありません。そのため、水疱や膿疱ができている部分をガーゼなどで覆ってあげれば幼稚園や小学校などを休む必要はありません。しかし、病変が広範囲にわたっている場合や全身症状のある場合には出席停止になる場合もあるとされています。また、プールの水を介して感染することはありませんが、水疱や膿疱、浸出液などがほかの人に触れる可能性が高いため、プールや水泳は控えた方がよいとされています。
とびひの治療法
とびひが疑われた場合には、患部が広がる前に皮膚科を受診しましょう。ごく軽度な場合を除き、治療には抗生剤の内服薬を使用します。さらに、抗菌作用を持つ外用剤を塗ることもあります。1週間以内に改善することが多いですが、細菌が生産する毒素が全身にまわると、高熱や皮膚がむける症状、腎臓の障害などが起こることがあります。
とびひの予防法
とびひの予防においては、皮膚を清潔に保つことが大切です。1日に1回以上は皮膚を洗いましょう。水だけではなく、石けんをしっかりと泡立てて、やさしく洗いましょう。
また、すでにとびひにかかってしまったのであれば、水疱や膿疱を潰さないように爪を短くきったり手を洗ったりするなど、症状の悪化を防ぐための対策を行いましょう。水疱や膿疱ができているうちは、湯船には浸からずにシャワーで済ませましょう。水疱やかさぶたをたっぷりの泡で洗い、やさしく洗い流してください。そして、患部を乾燥させてから外用剤を塗り、ガーゼなどで覆いましょう。
タオルなどは家族と共有しないよう注意しましょう。
オススメ記事
- 関連するオススメ記事がありません。
スキンケア基礎講座
- スキンケア基礎講座
- アロマテラピー
- クレンジング
- サプリメントの基礎
- サプリメントを学ぶ
- スカルプケア
- スキンケアの基本
- ヘア・髪の知識
- ボディケア
- 妊娠・出産・産後の肌
- 心とスキンケア
- 更年期のスキンケア
- 産後の肌とスキンケア
- 美容・美肌
- 美容によいとされる植物
- 美容成分の基礎知識
- 美白・抗酸化
- 美肌をつくる化粧品の基本
- 美顔器を使ったスキンケア
- 肌と女性ホルモン
- 赤ちゃんのスキンケア
- 頭皮のケアについて
- メイク講座
- 悩み別講座
- アトピー性皮膚炎
- いぼ
- かゆみ・皮膚掻痒症
- シミ・そばかす
- シワ
- すそわきが
- その他の発疹・皮膚病
- たるみ・ほうれい線
- デリケートゾーン
- ニキビ・吹き出物
- ヘルペス
- ほくろ
- まつげのトラブル
- むくみ
- わきが
- 体臭
- 便秘・デトックス
- 傷・傷跡
- 冷え性
- 口内炎・口周辺のトラブル
- 多汗症
- 女性のお悩みボディケア
- 性病・性感染症
- 日焼け・紫外線対策
- 毛嚢炎
- 毛穴・角栓
- 水虫・皮膚真菌症(白癬)
- 汗・ニオイ
- 湿疹・皮膚炎
- 火傷(やけど)
- 生理痛・生理前の不調
- 白斑
- 目の周辺のトラブル
- 粉瘤(ふんりゅう)
- 糖質制限
- 美白・くすみ・目の下のくま
- 肉割れ
- 肌のハリ・ツヤ
- 脱毛・ムダ毛処理
- 花粉症
- 蕁麻疹(じんましん)
- 虫・害虫の皮膚トラブル
- 赤ら顔
- 靴擦れ
- 頭皮疾患・脱毛症
- 顔の傷
- 顔太り
- 用語集
- お肌&からだ・用語
- スキンケア・用語
- 化粧品・用語
- 美容成分・用語
- 男の美容講座
- お悩み&トラブル肌講座
- メンズスキンケア基礎講座
- 育毛
- 美容医療
- アンチエイジング
- くま・目の下のくま
- シミ(しみ)・肝斑
- しわ(注入治療)
- タトゥー(刺青)除去治療
- たるみ・ほうれい線治療
- ニキビ治療
- バスト・胸のお悩み
- ボトックスの治療
- わきが(ワキガ)のお悩み
- 二重手術
- 切らない脂肪吸引・部分痩せ治療
- 女性の増毛(植毛・ウィッグ)
- 脂肪吸引
- 赤ら顔・肌の赤み
- 鍼灸(しんきゅう)治療
- 肌タイプ別講座