内容が最新ではない可能性がございますので予めご了承ください。
とびひ(伝染性膿痂疹)の原因と治療・予防法について
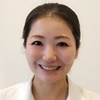
とびひの原因菌は、とびひの種類で異なります。原因菌に対して有効とされる治療薬を使用します。原因菌について自分で判断はできないので、医療機関を受診しましょう。ここでは、とびひの原因についてドクター監修の記事で解説します。

とびひを発症すると、皮膚の赤みや水疱、膿胞などが皮膚に現れます。似ている病気がいくつかあるので、安易に自己判断してはいけません。とびひの原因や治療法についてみていきましょう。
とびひ(伝染性膿痂疹)の原因
とびひには、水疱性膿痂疹(すいほうせいのうかしん)と痂皮性膿痂疹(かひせいのうかしん)があり、それぞれ原因となるウイルスが異なります。水疱性膿痂疹の原因菌は黄色ブドウ球菌、痂皮性膿痂疹はA群β溶結性レンサ球菌が多いです。痂皮性膿痂疹には、黄色ブドウ球菌との混合感染の場合もあります。
MRSAへの感染も
MRSAとは、メチシリン耐性黄色ブドウ球菌のことを指します。多数の抗生物質に対して耐性を持つため、一般的に用いられる抗生物質が効かないとされています。とびひが一向に改善しない場合には、MRSAの感染が疑われます。MRSAは、のどや鼻の入り口など湿気がある部位に付着しやすいといわれています。治療では、MRSAに対して効果が期待できる数少ない抗生物質の中から、病状に合わせて効果があると考えられるものを使用します。重症のやけどをした後や大きな手術をした後にMRSAにかかりやすいといわれています。
MRSAには、ドアノブなど不特定多数の人が触れるものを介して感染することが多いです。予防のために、手洗いうがいを徹底しましょう。
水疱が発生するとびひのメカニズム
水疱性膿痂疹では、黄色ブドウ球菌が生産する表皮剥脱毒素によって皮膚が侵されることで症状が現れます。表皮細胞は、デスモグレイン1を含む構造物で繋がれています。表皮剥脱毒素によってデスモグレイン1が破壊されることで、水疱が発生します。
とびひは乾燥肌の人が感染しやすい
とびひには、乾燥肌の人がなりやすいといわれています。肌が乾燥している状態では、肌のバリア機能が低下しているため、菌が肌の内部に入りやすくなっています。そのため、アトピー性皮膚炎などの患者は、とびひも発症しやすいとされています。
うつっても幼稚園や学校の登校は可能
黄色ブドウ球菌は鼻の中に多く常在しています。鼻の中に入れた指で皮膚の傷などに触れることで、黄色ブドウ球菌が肌の内部へと侵入します。また、黄色ブドウ球菌は肌にも存在しているので、傷ができるだけでとびひになる可能性があります。
水疱をひっかいた爪で他の部位をひっかくと、水疱が広がってしまいます。また、病変部が露出するので、その部位に触れることで、とびひがうつる可能性があります。とびひは、出席停止の処置の必要がないとされているので、発熱など全身症状がないのであれば、いつも通り出席しても構いません。また、出席する際には、患部をガーゼで保護することが大切です。
とびひは繰り返す病気?
とびひの原因となる黄色ブドウ球菌やA群β溶結性連鎖球菌に対しては、十分な免疫が作られないため、何度でもとびひになる可能性があります。
汗や虫刺されが多い夏にまん延する
夏は、あせもや虫さされなどによって皮膚に傷ができ、そこから黄色ブドウ球菌などが侵入してとびひを発症します。特に水疱性膿痂疹は注意が必要です。痂皮性膿痂疹は季節に関係なく発症する可能性があります。
とびひの検査方法
水疱性膿痂疹の症状だけで診断できない場合は、水疱や膿胞の内部にある液体を培養し、顕微鏡で観察して原因菌を突き止めます。痂皮性膿痂疹は、重症化すると腎機能が低下することがあるので、尿検査を行う場合があります。
とびひの治療方法
とびひの治療は、それぞれの原因菌に対して有効とされる抗生物質を内服したり外用したりします。かゆみが強い場合には、抗ヒスタミン剤を使用することがあります。症状が軽度の場合には、水疱や膿胞に含まれる液体を取り除き、抗生物質の外用剤を塗ってからガーゼで覆います。ガーゼは1日数回程度取替えることが推奨されます。抗生物質は医師の指示通りに飲みきりましょう。10日程度行うことが多いです。
とびひの予防方法
とびひの予防として、次のようなことを心がけましょう。
患部が悪化しないように清潔にする
シャワーなどで患部を洗いましょう。石けんをしっかり泡立てて、優しく洗ってください。
皮膚の病気を治療する
湿疹やアトピー性皮膚炎などの治療を受けて、少しでも肌のバリア機能を低下させないようにしましょう。
傷や擦り傷などはすぐに治療する
外傷をそのままにしておくと、そこから原因菌が侵入するおそれがあるので、できるだけ早く治療することが大切です。
常に手のひらをきれいにする
こまめに手を洗うとともに、患部を掻き壊さないよう爪を短く切っておきましょう。
オススメ記事
- 関連するオススメ記事がありません。
スキンケア基礎講座
- スキンケア基礎講座
- アロマテラピー
- クレンジング
- サプリメントの基礎
- サプリメントを学ぶ
- スカルプケア
- スキンケアの基本
- ヘア・髪の知識
- ボディケア
- 妊娠・出産・産後の肌
- 心とスキンケア
- 更年期のスキンケア
- 産後の肌とスキンケア
- 美容・美肌
- 美容によいとされる植物
- 美容成分の基礎知識
- 美白・抗酸化
- 美肌をつくる化粧品の基本
- 美顔器を使ったスキンケア
- 肌と女性ホルモン
- 赤ちゃんのスキンケア
- 頭皮のケアについて
- メイク講座
- 悩み別講座
- アトピー性皮膚炎
- いぼ
- かゆみ・皮膚掻痒症
- シミ・そばかす
- シワ
- すそわきが
- その他の発疹・皮膚病
- たるみ・ほうれい線
- デリケートゾーン
- ニキビ・吹き出物
- ヘルペス
- ほくろ
- まつげのトラブル
- むくみ
- わきが
- 体臭
- 便秘・デトックス
- 傷・傷跡
- 冷え性
- 口内炎・口周辺のトラブル
- 多汗症
- 女性のお悩みボディケア
- 性病・性感染症
- 日焼け・紫外線対策
- 毛嚢炎
- 毛穴・角栓
- 水虫・皮膚真菌症(白癬)
- 汗・ニオイ
- 湿疹・皮膚炎
- 火傷(やけど)
- 生理痛・生理前の不調
- 白斑
- 目の周辺のトラブル
- 粉瘤(ふんりゅう)
- 糖質制限
- 美白・くすみ・目の下のくま
- 肉割れ
- 肌のハリ・ツヤ
- 脱毛・ムダ毛処理
- 花粉症
- 蕁麻疹(じんましん)
- 虫・害虫の皮膚トラブル
- 赤ら顔
- 靴擦れ
- 頭皮疾患・脱毛症
- 顔の傷
- 顔太り
- 用語集
- お肌&からだ・用語
- スキンケア・用語
- 化粧品・用語
- 美容成分・用語
- 男の美容講座
- お悩み&トラブル肌講座
- メンズスキンケア基礎講座
- 育毛
- 美容医療
- アンチエイジング
- くま・目の下のくま
- シミ(しみ)・肝斑
- しわ(注入治療)
- タトゥー(刺青)除去治療
- たるみ・ほうれい線治療
- ニキビ治療
- バスト・胸のお悩み
- ボトックスの治療
- わきが(ワキガ)のお悩み
- 二重手術
- 切らない脂肪吸引・部分痩せ治療
- 女性の増毛(植毛・ウィッグ)
- 脂肪吸引
- 赤ら顔・肌の赤み
- 鍼灸(しんきゅう)治療
- 肌タイプ別講座